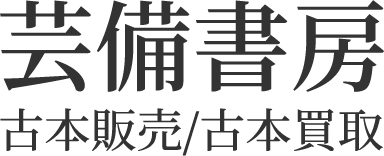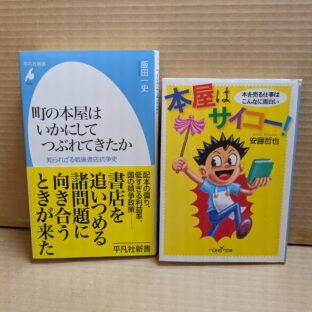2025.5.11 春の夜長の書評コーナー 町の本屋はいかにしてつぶれてきたか 飯田一史 平凡社新書
5月の2回目の書評は、「町の本屋はいかにしてつぶれてきたか 飯田一史 平凡社新書」を紹介したいと思います。
副題に「知られざる戦後書店抗争史」とあるとおり、戦後の新刊書店の栄枯盛衰について書かれたものです。最近の、新刊書店の数が減っている、文化の危機だ、新刊書を売るだけでは経営が成り立たない、といった書店の危機問題について、この本では「(新刊)書店には、大手資本の大型書店と、家族経営の小規模な町の本屋があるが、町の本屋は昔から経営が厳しかった」と述べています。
まず、日本の書籍流通についてふれ、再版維持制度というものが、書店にとって一律に有利なものではなく、大型書店にとっては値引き販売ができない、出版社・取次にとってはたくさん販売してくれる大型書店に売れ筋の本を多く配本する方が効率がいい、法人外商や職場外商といった訪問販売専門出版社の台頭(書店を通さずに本を販売する出版社)など、以前から町の本屋にとっては逆風が吹いていたと述べています。
その中で、町の本屋では、外商や棚づくり、取次のおまかせ配本に頼らない独自の仕入れ、書籍、雑誌以外に文房具、CD、ビデオ、DVD、ゲーム、レンタルへの多角化など、工夫をこらしたところは生き残り、そうではないところは、新たに出店した大型書店との競合に負け、数を減らしてきたと述べています。上記の工夫の言った点は「本屋はサイコー! 安藤哲也 新潮OH!文庫 新潮社」を参照ください
そのうち、Amazonをはじめとするネット通販の台頭、電子書籍の台頭、雑誌の売り上げ減少、がきて、新刊書店、取次ともに昨今、経営が非常に厳しくなってきたと述べています。
ただ、書籍、コミック、雑誌のうち、①書籍は減っていない、②電子書籍分野ではコミック分野での売り上げが伸びており、出版社はそれほど困っていない(取次、書店は困っている)、③雑誌は確かに部数も減っており、それに伴い広告収入の減少、書店へのリピーター客の減少、雑誌流通をベースとした配本システムの劣化など、出版社・取次・書店とも大きな影響を与えています。
また、図書館についても触れていますが、図書館の購入需要を、取次からのパターン配本では町の本屋が対応できず、TRC(図書館流通センター)に負けてしまった点を指摘しています。
その他、キオスク、コンビニにおける文庫本、雑誌販売に対しても、町の本屋はうまく対応できなかった点を指摘しています。
一言でいうと、町の本屋の経営危機というのは、今に始まったことではなく、昔からあったということ、そして書籍、コミック、雑誌でいうとそれぞれに衰退の状況は異なっており、コミックについては電子書籍への対応、雑誌については媒体としての価値低下(娯楽、ニュース媒体として、ネットに負けている)、があげられます。また、AmazonやBookoffのような大手ネット通販、リサイクル業者(新古書店)においても、書籍以外の商材の多角化が進んでいることを指摘しています。
少なくとも、取次や書店(大手新刊書店、町の本屋とも)における制度疲労はまぬがれないと言えます。末尾に最近の新しい動きとして「ブックカフェ・独立系書店」「シェア型書店」を挙げていますが、これについてはまだ評価するには時期尚早としています。
このように町の本屋の危機は、今に始まったことではなく、昔からあることだというのが、主な内容ですが、それぞれの要因分析等について身につまされるものがあります。1冊にまとめる性質上仕方ないとしても、個人経営、中小零細の古本屋についても含めた分析もしていただけたらと思いました。
今回の書評はここまでにします。次回もお楽しみに。
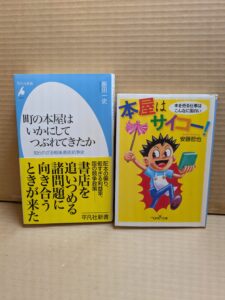
関連情報