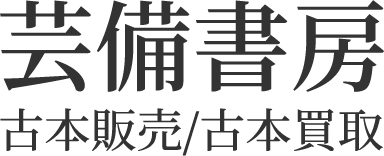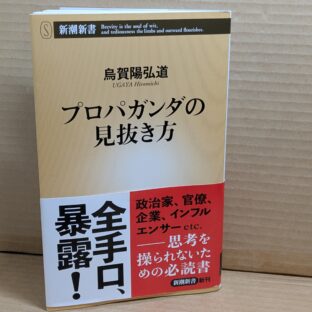2025.3.18 春の夜長の書評コーナー プロパガンダの見抜き方 烏賀陽弘道 新潮新書
3月の3回目の書評は、「プロパガンダの見抜き方 烏賀陽弘道 新潮新書」を紹介したいと思います。
昨今は、財務省解体デモや、NHK党立花襲撃事件や、兵庫県知事選挙など、SNSをつかった政治的ムーブメントが起こっている中で、プロパガンダというものがいかにその影響力を発揮しているかを解説している本です。
著者はもともと朝日新聞の記者をしていて、その時に「宣伝につかわれてはならない」ということを肝に銘じたそうです。新聞社はあくまで国民の側に立つべきで、特定の企業団体役所の広告宣伝のお先棒を担いではならず、事実の調査報道に徹するということを強く認識したそうです。
とはいえ、プロパガンダ(広報・PR)とはそもそも、情報を流す側から、多数の受け手に対して、明確な特定の意図・思惑を伝えることであり、その中には当然真実も含まれるので(逆に100%嘘というのは信じてもらえない)、プロパガンダなのか、事実(真実)なのかの見極めるポイントをこの本で解説しています。解説のなかで、プロパガンダの歴史・発達過程、プロパガンダの特徴、プロパガンダの実例について述べています。
例えば、プロパガンダの起源は、カトリックの布教活動が起源であり、口伝・説法(あと絵画・音楽・彫刻など)から、活版印刷・印刷メディア→映画・テレビ→インターネット→スマホ・SNSへと進化していると分析しており、また、それぞれの進化の過程における実例について紹介しています。
そして、プロパガンダの特徴として、①物語性をもたせる(いわゆる5W1H)、②わかりやすいこと、キャラが立っていることなどである。具体的には、勧善懲悪的なもの、例えば、既得権益(主流派・日本だと成人男性特におじさん)vs社会的弱者(若い女性、子ども、弱い年寄り、なんのとりえもないごく普通のありふれた人など)なり社会的弱者を救う上級国民などが好まれる(水戸黄門などの時代劇、アニメにある正義は勝つ的な物語)のような物語、美談が好まれるし、その中でキャラが立っていること、例えばゆるキャラなどのように親しみやすくかつ目立つのが効果的とされている。またわかりやすさのためにワンフレーズを何度も繰り返し繰り返し多用する(例えば、自民党をぶっ壊す、悪の枢軸、など)などといった点を挙げています。
私は、この本を読んで、プロパガンダの特徴をつかみ、そのうえで、受け手側が、受けた情報のうち、どこまでが事実で、どこからが事実でない(いわゆる発信者側の意図・思惑がどこに内包されているか)という判断リテラシーをつけることが必要だと感じました。また、これだけYoutube、SNSが普及している中で、冒頭にあげたような政治的ムーブメントが起こっており、その中には多分にプロパガンダが混じっているだろうなと自省も含めて考えさせられました。
今回はここまでにします。次回もお楽しみに。

関連情報