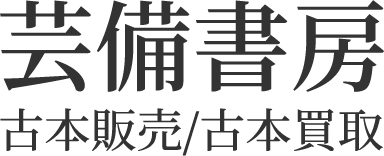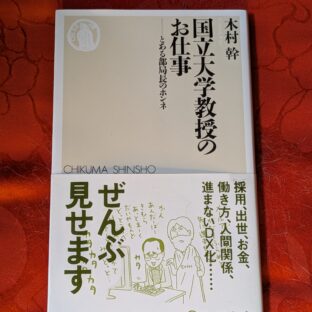2025.7.7 夏の夜長の書評コーナー 国立大学教授のお仕事 木村幹 ちくま新書
まだ7月上旬だというのに梅雨あけで、どうなっているんだろうという今日この頃です。
さて、今回紹介する本ですが、国立大学教授のお仕事 木村幹 ちくま新書 です。
当店では、ありがたいことに、大学の先生、大学院生、図書館、博物館等に古書を納品させていただく機会が多いです。そこで、大学の先生の昨今のお仕事事情を知るのに良さそうな本だなと手に取った次第です。
著者の木村先生は、京都大学、京都大学大学院(比較政治学(韓国の政治文化))を経て、愛媛大学法文学部、神戸大学の教員になり、現在は神戸大学大学院国際協力研究科教授をされています。
本の中に、とある1週間のスケジュールが紹介されていますが、とても忙しいのにびっくりしました。特に学内事務(会議や決裁、文科省への書類作成など)が多く、そのほかにもマスコミ対応、学会事務などがあり、そのほかに教育活動(大学での講義、学生への指導など)、さらに本来の研究活動と続いています。
昔と比べると、明らかに学内事務が増大しているとともに、教育活動の負担も増しているようです。その結果研究活動に割く時間が減ってるようです。
こうなってしまったのは、文科省による大学改革(予算の削減、独立行政法人化(国立大学法人))の影響が非常に大きいようです。研究予算の削減に伴い、科研費の申請をしたり、外から研究費用を引っ張ってくるための営業活動(そのためにマスコミ対応したり、企業との共同研究プロジェクトを進める等)の負担が大きいようです。
もちろん、国公立か私立か、大学の規模(学部、大学院)、大学のレベル、文系か理系か、単科大学か総合大学かによっても違ってくるようですが、年々削減される研究費の中から、当店から古書をお求めいただいていることを知り、身の引き締まる思いです。
しかし、この本に書かれているような、昨今の大学やアカデミズムの実態をみるにつき、日本はこれでいいのだろうか?と改めて思います。
当店は微力ながら、研究活動の一助となるべく、古書仕入販売を続けていく所存ですので、皆様よろしくお願いいたします。
なんだか書評といえるか微妙なところですが、今回の書評はここまでにします。次回もお楽しみに。
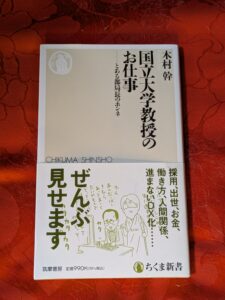
関連情報